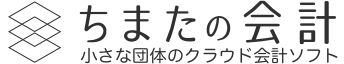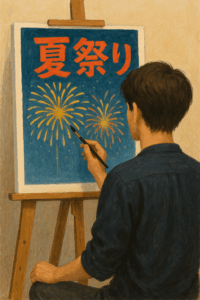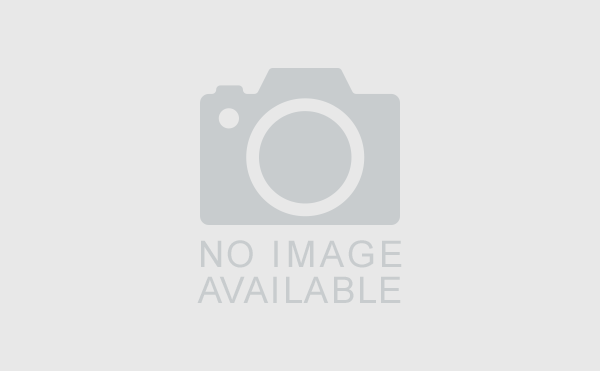ちまたの会計とは?無料で使える地域団体向け会計ツールを徹底解説【操作・帳簿出力・引き継ぎも簡単】

~日々の記録から収支決算書までサクサクっと終わらせる~
帳簿の作成、会計報告、引き継ぎまで。
「ちまたの会計」なら、地域団体の面倒な会計作業をすべてサクッとこなせます。しかも無料。スマホにも対応しているので、外出先でも記録OKです。
目次
1.地域団体の会計が驚くほど簡単になる「ちまたの会計」の魅力

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです:
- 簿記知識がなくても使える設計
- 会計報告に必要な帳簿が自動で作成できる
- スマホ・タブレット対応でいつでもどこでも操作可能
会計作業に不慣れな地域団体の担当者にとって、「ちまたの会計」は非常に頼れる存在です。特に、簿記の知識がない人でも直感的に扱えるインターフェースが魅力で、会計処理にかかる時間やストレスを大幅に削減できます。ここでは、そんな「ちまたの会計」の具体的な使いやすさや利便性について、3つの視点からご紹介します。
簿記知識がなくても使える設計
「ちまたの会計」は、簿記の専門知識がない人でも迷わず使えるように設計されています。取引内容を選択肢から選ぶだけで、複式簿記の仕訳が自動で行われ、帳簿に正確に反映されます。入力画面もわかりやすく、「収入」「支出」などの区分ごとに整理されており、操作に迷うことがありません。
また、勘定科目や仕訳ルールはあらかじめ設定されているため、自分で複雑な会計処理を考える必要もなし。これにより、「間違えたらどうしよう」という不安を軽減し、誰でも安心して使えるのが大きな特長です。
会計報告に必要な帳簿が自動で作成できる
「ちまたの会計」では、入力された日々の取引データをもとに、会計報告に必要な帳簿類が自動で作成されます。たとえば、年間の収支決算書や取引台帳などがボタンひとつで出力できるため、年度末の報告作業がスムーズに進みます。
この自動生成機能により、手書きやExcelでの集計にありがちな集計ミスや転記漏れのリスクが大きく減少します。また、帳簿はPDFやExcel形式で保存・印刷ができるので、行政や自治会本部への提出にも対応可能です。
スマホ・タブレット対応でいつでもどこでも操作可能
外出先や集会所など、パソコンが手元にない環境でも「ちまたの会計」は利用可能です。スマートフォンやタブレットにも対応しており、ブラウザを開けばすぐに入力画面へアクセスできます。アプリのインストール不要で、IDとパスワードさえあればどの端末からでも操作できる点が利便性を高めています。
ちょっとした支払いをその場で記録したり、確認したい帳簿をすぐ表示したりと、場所にとらわれずに作業ができるのは大きな強みです。担当者の交代やチームでの作業分担にも柔軟に対応できる点も、地域団体にとっては心強いポイントです。
2.「ちまたの会計」が向いている団体

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです:
- ちまたの会計が活躍する団体の特徴(町内会・老人クラブ・ボランティア団体など)
- 注意が必要なケース(部門別会計が必要、詳細な予算管理が求められる団体)
- 導入前に確認しておきたいポイント
「ちまたの会計」は多くの地域団体にとって有用なツールですが、すべての団体に完全に適しているわけではありません。利用に向いている団体とそうでない団体には、目的や業務内容に応じた違いがあります。この章では、どのような団体にとって効果的なのか、また導入前に注意すべき点について詳しく見ていきます。
ちまたの会計が活躍する団体の特徴
「ちまたの会計」が最も活躍するのは、町内会や老人クラブ、地域のボランティア団体など、比較的シンプルな会計処理を求められる団体です。たとえば、以下のような条件に当てはまる団体には特に向いています。
- 年間の取引件数が多くない(2000伝票以下)
- 1団体で個別部門の収支管理が不要
- 資金の出入りが「収入」「支出」でほぼ完結する ※仮払・立替金などは別途銀行設定で代替可能
- 会計報告が年1回程度で済む
このような団体であれば、「ちまたの会計」の自動帳簿機能と簡潔な操作性が非常に役立ちます。会計処理を効率化することで、担当者の負担を大幅に軽減できます。
注意が必要なケース
一方で、活動内容が多岐にわたるNPO法人や補助金の使途が厳密に求められる団体では、「ちまたの会計」では機能が足りない可能性があります。特に以下のようなケースでは注意が必要です。
- 部門別に収支を分けて記録・報告する必要がある
- 予算に対する実績管理をきめ細かく行いたい
- プロジェクトごとの支出内訳を細かく記録したい
- 月次や四半期ごとに細かい分析・報告が必要
このようなニーズがある場合は、freee会計など、部門管理や分析機能が充実したソフトのほうが適しているかもしれません。
3.会計ソフトの比較【マトリックスで解説】

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです:
- 主要4サービスの比較早見表(ちまた/freee/フリーウェイ/Excel)
- 「ちまたの会計」の位置づけと活用シーン
会計ソフトは数多く存在しますが、団体の性格や会計担当者のスキルによって、適したツールは異なります。ここでは「ちまたの会計」を含む主要4ツールを比較し、それぞれの強みや向いているユーザー像を明らかにします。あわせて、目的に応じた選び方のヒントもご紹介します。
主要4サービスの比較早見表(ちまた/freee/フリーウェイ/Excel)
以下の表は、地域団体でよく検討される4つの会計ツールを比較したものです。料金、操作性、部門別管理、帳簿出力、対象ユーザーの傾向などをまとめました。
| 項目 | ちまたの会計 | freee会計 (NPOプラン) | フリーウェイ 経理Lite | Excel(自作) |
| 料金 | 無料 | 有料(年額26,136円〜) | 無料 | 無料(Excel保有前提) |
| 操作性 | ◎ | △(機能多) | ○(会計知識要) | △(手作業が多い) |
| スマホ対応 | ◎ | ◎ | △ | △(アプリなし) |
| 部門別管理 | × | ◎ | △(簡易対応) | ◎(構造次第) |
| 自動帳簿作成・出力 | ◎ | ◎ | △(手動が多い) | △(関数・手動) |
| 銀行連動 | なし | あり | あり | なし |
| 簿記管理 | 単式 | 複式 | 複式 | ‐ |
| 推奨団体 | 小規模団体・初心者向け | 中〜大規模・法人向け | 会計経験者がいる団体 | 自作に慣れている担当者 |
このように、機能の豊富さだけでなく「誰が使うか」「どこまで求めるか」によって、選ぶべきツールは大きく変わります。
「ちまたの会計」の位置づけと活用シーン
「ちまたの会計」は“簡単・無料・直感操作”に特化した地域団体向けツールです。機能の幅広さではfreee会計に及びませんが、「必要最低限のことをミスなくこなす」点においては非常に優れています。
特に次のような場合は有効です。
- はじめて会計を担当する人に引き継ぐとき
- パソコンが操作が苦手でも安心して使える環境を整えたいとき
- これまで自作したエクセルでの引継ぎが大変だった
- スマホの操作で簡単に入力管理がしたい
- 補助金や町内会費のシンプルな記録だけで済む場合
“便利だけど難しい”ではなく、“必要十分で簡単”という点が「ちまたの会計」です。
4.「ちまたの会計」のメリット・デメリット

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです:
- 無料なのに充実した機能
- 比較的やさしい操作性
- サポート・マニュアルの充実度
- 部門別管理や詳細分析には不向き
どんなツールにも一長一短があるように、「ちまたの会計」にも明確なメリットと制限があります。この章では、導入前に知っておくべき利点と課題を整理し、納得したうえで選択できるようお手伝いします。
無料なのに充実した機能
「ちまたの会計」は、完全無料でありながら、帳簿作成・収支決算・印刷出力まで一通りの会計処理に対応しています。特に地域団体の会計に必要とされる最低限の機能がそろっているため、有料ソフトに引けを取らない実用性があります。
日々の記録を入力するだけで、収支決算書や取引台帳が自動で生成される点は、会計初心者にとって非常にありがたい設計です。会計ソフト導入のハードルを大きく下げる存在だといえるでしょう。
比較的やさしい操作性
操作画面はシンプルかつ見やすく設計されており、感覚的に使える工夫が施されています。大きめの文字、選択式の入力項目、分かりやすいメニュー構成など、UI(ユーザーインターフェース)を意識した作りです。
また、スマホでも操作が可能なため、共有作業や、会議中に即時入力といった活用法も広がります。デジタルに不慣れな方でも安心してスタートできる会計ツールといえます。
サポート・マニュアルの充実度
「ちまたの会計」公式サイトには、図解付きの操作マニュアルや、Q&A形式のヘルプ回答が用意されています。設定の手順や帳簿の出力方法など、つまずきやすいポイントを参照・確認可能です。
部門別管理や詳細分析には不向き
一方で、「ちまたの会計」はシンプルさを重視している分、高度な機能には対応していません。たとえば、次のような要望がある場合は別ソフトの検討が必要です。
- プロジェクト単位や部門別で収支を分けて管理したい
- 複式簿記で管理したい
比較表にも示している通り、詳細管理はできないため、あくまで基本的な会計業務を簡単に済ませることを主眼にした設計だと理解しておく必要があります。
5.導入までのステップと初期設定の流れ

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです:
- 登録方法とログインの手順
- 団体名・収支分類など初期設定のやり方
- データの保存・引き継ぎ方法と注意点
「ちまたの会計」は、インストール不要・無料で始められるクラウドサービスです。ただし、スムーズに活用を始めるためには、最初の導入ステップと初期設定が重要です。この章では、登録から設定完了までの流れをわかりやすく解説します。
ちまたの会計にログインする手順と注意点
「ちまたの会計」は、公式サイトにアクセスし、無料ユーザー登録を行うだけで利用が開始できます。登録に必要な情報は次のとおりです。
- アカウント名 【要注意】変更不可 (引継ぎ管理しやすい名称をつけましょう)
- メールアドレス ※変更できます(ただし、1メールアドレス1アカウントまで)
- 任意のパスワード
登録が完了すると、すぐにログイン可能となり、団体情報の入力画面へ移動します。ブラウザ型のため、アプリのダウンロードやPCへのインストールは不要です。IDとパスワードさえあれば、どの端末からでも利用できます。
団体名・収支分類など初期設定のやり方
最初に行うべき初期設定は、以下の3つです。1つのアカウントで、5団体まで作成管理ができます。
- 団体名の登録:帳簿や収支報告書に表示される名称になります。
- 収支分類の選択:デフォルトで用意されている科目を使うか、自団体に合わせてカスタマイズも可能です。
- 会計年度の設定:例年の会計期間(例:4月~翌3月)を設定します。
これらの設定は、後からでも変更できますが、最初にしっかり整えておくことで、スムーズな帳簿作成が可能になります。
データの管理・引き継ぎ方法と注意点
「ちまたの会計」はクラウド上にデータを保存する仕組みのため、個別に保存作業を行わなくても、常に最新の状態が記録されます。操作ミスや端末の故障によるデータ消失の心配が少ないのも安心材料のひとつです。
ただし、次の会計担当者に引き継ぐ際には以下のような点に注意しましょう。
- アカウント名 とパスワードの管理
- 引継ぎ後の不慣れな操作でデータが変更されないように、
年度毎の情報バックアップを出力管理しておく&印刷管理しておく - 操作方法を指南し、次年度の入力がスタートできる所まで一緒に確認する
- 管理者が複数人いる場合は事前に運用ルールを決めておく
引き継ぎの際は、年度末にPDFやExcelで帳簿をダウンロードしておくと、紙ベースでの説明や確認にも役立ちますね。
6.「収入」「支出」の入力方法と帳簿の出力手順
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです:
- 日々の取引入力(収入・支出)
- 勘定科目の設定と活用方法
- 帳簿の出力(Excel、PDF)と提出用資料の作成
「ちまたの会計」は、収入・支出の入力が簡単にできるよう設計されています。会計作業の大半を占める“記録”と“出力”の操作がスムーズに行えるため、初心者でも戸惑うことなく帳簿を整えることが可能です。この章では、実務に即した使い方・操作の流れをご紹介します。
日々の取引入力(収入・支出)
収入や支出の入力は、メニューから「取引の記録」を選び、以下の情報をフォームに入力するだけです。
- 取引日
- 区分(収入/支出)
- 金額
- 相手先・内容
- 勘定科目(選択式)
入力は1件ごとに行い、保存を押せば即座に帳簿に反映されます。現金出納管理も明確に分けて記録できます。これにより、領収書の整理や年度末のまとめ作業が格段にラクになります。
勘定科目の設定と活用方法
初期状態では「会費」「寄付金」「備品費」などの代表的な科目が用意されていますが、団体に応じて自由に削除・追加・編集が可能です。たとえば:
- イベント収入・支出
- 補助金収入
- 交通費・通信費
といった独自科目を作成し、より詳細に記録を分けることができます。
また、科目ごとの合計や割合も自動で集計されるため、決算書の内容に説得力が増し、会員や行政への説明資料としても有効に活用できます。
帳簿の出力(Excel、PDF)と提出用資料の作成
記録した取引データは、いつでも帳簿形式で出力可能です。主な出力資料には以下があります。
- 現金・銀行別の出納帳
- 収支決算書
- 収支予算書
- 科目別台帳
出力形式はPDFまたはエクセルが選べ、印刷して配布したり、メール添付で提出する際にも便利です。エクセルに出力することもできることから、ちまたの会計を必要書類をつくるための補助に使うという考え方もできます。
7.よくある質問と導入時の不安を解消するQ&A

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです:
- セキュリティは大丈夫?
- スマホだけで運用できる?
- 次の会計担当者への引き継ぎはどうする?
- ちまたの会計を試すには?デモ体験
「ちまたの会計」を導入する前に、多くの会計担当者が不安に感じるのが“使いこなせるか”“安全か”“引き継ぎはどうするか”という点です。ここでは、導入時によくある質問とその答えをQ&A形式で整理しました。
セキュリティは大丈夫?
はい、「ちまたの会計」は通信の暗号化(SSL)が施されており、通信経路の安全性は確保されています。
また、すべてのデータはクラウド上に保存され、端末側には残りません。これにより、端末の紛失・故障などによる情報漏洩リスクも低くなっています。
ただし、パスワード管理やログイン情報の取り扱いには十分注意が必要です。特に共有で使用する場合は、定期的なパスワード変更や閲覧制限を心がけましょう。
スマホだけで運用できる?
はい、スマートフォンやタブレットだけでも基本的な入力・出力作業は問題なく行えます。ブラウザでアクセスできるため、専用アプリのインストールも不要です。
画面はモバイル端末向けに最適化されており、入力項目の選択や帳簿の確認などもスムーズに行えます。ただし、長文の入力やPDFの細かなレイアウト調整にはパソコンの方が操作しやすい場面もあります。
次の会計担当者への引き継ぎはどうする?
次の担当者にスムーズに引き継ぐためには、以下の2点が重要です。
- ログイン情報(アカウント・メールアドレス・パスワード)の確実な共有
- 引き継ぎ時の簡単な操作マニュアル、また使い方の説明
公式マニュアルを印刷して手渡す、簡単な操作メモを作成しておくなど、デジタルが苦手な方でも使える工夫が効果的です。
また、年度が切り替わるタイミングで引き継ぎを行うと、帳簿の区切りが明確になり、新担当者が混乱しにくくなります。
ちまたの会計を試すには?デモ体験
ちまたの会計では、デモ体験アカウントが用意されています。パソコンやスマホから入って実際にどんな感じか体感してみましょう。
⇒リンク: デモサイト - ちまたの会計
8.こんなこともできる!~事業管理や仮払・立替金処理も~
補助金事業ごとの管理や、仮払・立替金の管理もできるの?上手く使えばできちゃいます。
【応用編】補助金事業ごとの管理方法(科目管理)


補助金は活用範囲が制限されているため、その事業毎に管理したいという声があるかと思います。最終の収支報告書の提出もあるためそのフォーマットに則した管理ができると嬉しいですよね。ちまたの会計では、事業毎の管理はできないのでしょうか?
結論として、「団体運営」「事業」で科目分類を管理する方法があります。
「科目分類」と「科目」の設定を上手く使うことで、収支決算書には事業毎の状況が見える状態で出力することが可能です。事業毎に手作業で科目設定が必要ですが、一度つくればその後は大きな手間なく作業ができると思います。
ただし、科目管理は団体全体でしかできないため、事業ごとの科目別‐台帳管理は出力できない点にはご注意ください。
(おまけ情報:時系列でもいいから事業レシート情報管理したい!⇒「銀行」設定で、補助金という銀行を設定をすれば「預金出納」として利用状況を確認することは可能です。)
【応用編】仮払・立替金などの管理方法
団体の会員が立て替えるという場合があるのではないでしょうか?その状況を帳簿で管理したい!そんな場合には、以下のように設定・操作で代替できます。
・①立替金の口座をつくる
・②立替金が発生した場合、Aさんのレシート処理を「支出:立替金口座(仮設置)」からしたことにする(摘要に支払った方の名前や備考を記入しておくとよい)
・③立替金を実際にAさんに支払った場合、振替処理「銀行⇒立替金口座(仮設置)」を行う。
これによって、預金出納帳で立替金処理の状況が確認できます。
登録はこちら
今すぐ使い始めたい方は、以下のリンクから無料登録が可能です。
登録はメールアドレスとパスワードの設定だけで完了します。
面倒なインストールや審査は一切不要です。まずはお気軽に、実際の画面を触ってみてください。
✅ まとめ:地域団体の“ちょうどいい”会計ツール
本記事では、「ちまたの会計」の特徴や導入の流れ、他ツールとの比較を通して、その魅力と注意点を整理してきました。ここで改めて、ポイントを簡潔に振り返ります。
✔ 本記事の要点まとめ
- 簿記知識がなくても使えるシンプル設計で、町内会・老人クラブ・小規模ボランティア団体などに特に適している
- 部門別管理や詳細な分析が必要な団体には、他の会計ソフトの方が適している場合も
- 「ちまたの会計」は完全無料ながら、帳簿出力や決算書作成まで対応可能な優秀ツール
📝 総括
「ちまたの会計」は、誰もが“なんとなく不安”に感じていた地域会計のハードルを、大きく下げてくれる存在です。
「できる人がやる」のではなく、「誰でも使える」ことを前提に設計されたこのツールを、まずは気軽に試してみませんか?
未来の会計担当者にも引き継ぎやすい、シンプルで安心な仕組みづくりの第一歩となるはずです。
【ちまたの会計運営サイトより抜粋です】
<ご寄附によるご支援のお願い>
ちまたの会計は、任意団体・非営利組織などの団体が無料で利用できる会計クラウドサービスです。私たちは会計サービスを長期に提供しつつ、さらに改善していきたいと考えています。ちまたの会計を気に入っていただけたら、ぜひ寄付を検討してください!寄付によって、ちまたの会計の継続を支えていただきますようお願いいたします。
<ちまたの会計が寄付を必要とする理由>
長期的な存続のため資金を必要としています。アプリケーションを何千人ものユーザーにご利用いただくには、それなりの規模のインフラストラクチャ(サーバー・通信・セキュリティ)を維持していかなければなりません。ちまたの会計が存続し進化を続けられるよう、みなさまの支援を必要としており、ご寄付をお願いしたくよろしくお願いいたします。
皆さんからいただいた寄付金は ちまたの会計 の開発費・運営費・インフラストラクチャ・ドメイン代などに充てられます。
<寄付の金額>
一口 1,000円 ~ となっております。
ちまたの会計がお役に立てるようでしたら、一口 1,000円 , 三口 3,000円 , 五口 5,000円 , 何口でも受け付けております。
⇒リンク先 ちまたの会計からご寄附のお願い
使ってみたコメントや気になる点などあれば、「お問合せ」にご連絡ください。