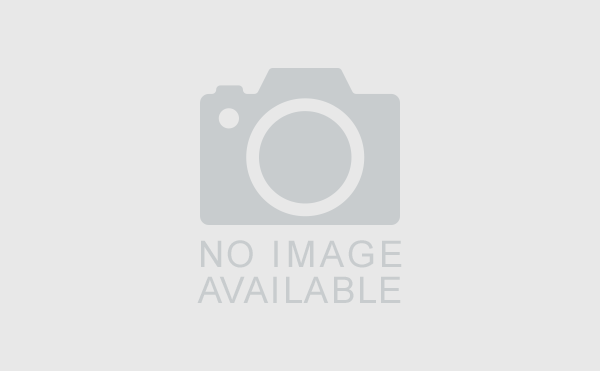家の相続・登記の基礎知識:行政書士と司法書士の違いと手続きの流れ

はじめに
「長年住んでいない実家があるけど、固定資産税は毎年払っている」
実は、その固定資産税の納付書には、「〇〇様 外〇名」と書かれていませんか?
「固定資産税は払っているけど名義は複数人」という相談事例は、特に相続登記をせずに放置された空き家で非常に多く見られます。
空き家をそのままにしておくと、将来的に売却や活用を考えた際に、名義が複数人に分散していることで手続きが複雑になり、思い通りに進まなくなるリスクがあります。
特に2024年4月からは相続登記が義務化されます。相続が発生したら、たとえ空き家であっても、相続や空き家売却を見据えた登記の重要性は高まる一方です。
本記事では、この複雑な手続きを円滑に進めるために知っておくべき行政書士と司法書士の役割の違い、そして相続登記の基本的な知識と流れを解説します。
| 【豆知識】 固定資産税の名義人 ・相続登記をせずに放置すると、不動産の名義は法定相続人全員の共有状態になりやすくなります。 ・固定資産税の納税義務は、その年の1月1日時点の所有者(共有者)全員にあります。 ・ただし、納税通知書は、便宜上、**「代表者(管理人)」**にまとめて届く仕組みになっています(宛名に「○○外」と記載されることも多いです)。 実務的には代表者がまとめて支払うケースが多いですが、税法上の義務は全員にあります。 ・固定資産税は原則、所得税の控除対象外です。ただし、その不動産が事業用や賃貸用である場合は、必要経費として算入が可能です。 |
目次
第1章 専門家の違いを理解する
相続や空き家の問題は、複数の専門家が関わる可能性があります。特に「士業」と呼ばれる専門家の中で、誰に何を依頼できるのかを理解することが、問題解決への近道です。
行政書士ができること/できないこと
行政書士は、官公署に提出する書類の作成や提出の代理を主な業務としています。登記申請こそできませんが、相続の初期段階における「手続きの準備」をサポートできます。
- 〇戸籍収集による相続人確定
- 〇財産目録の作成
- 〇遺産分割協議書の作成サポート
これは司法書士もできることですが、「相続の手続きを始めたいが、何から手をつけていいか分からない」という方の入口の相談役となりえます。以下は、行政書士ができないことです。
- ✕登記申請の代理(司法書士の独占業務)
- ✕相続人同士の代理交渉や紛争解決(弁護士の独占業務)
司法書士の独占業務(登記手続)
司法書士は、不動産や会社に関する「登記」の専門家です。
- 独占業務:
- 不動産登記(相続登記、売買による所有権移転登記など)の申請代理
- 裁判所や検察庁に提出する書類の作成
- 相続においては、不動産の名義変更手続き(相続登記)を唯一、依頼できる専門家です。
弁護士に相談すべきケース(相続争い、紛争)
弁護士は、法律に関する全ての業務を行うことができ、特に紛争性のある案件に対応できます。
- 相談すべきケース:
- 遺産の分け方について相続人同士で争いになっている(相続争い、紛争)
- 代理人として他の相続人と交渉する必要がある
社労士は?(不動産登記には関与しない)
ちなみに、社労士(社会保険労務士)は、労働・社会保険に関する手続きや労務管理の専門家であり、不動産登記には一切関与しません。
専門家フローチャート(相続・不動産)
| 目的 | 専門家 |
| 不動産の名義変更(登記) | 司法書士 |
| 相続人・財産調査、書類作成 | 行政書士、司法書士 |
| 相続人間での交渉・紛争解決 | 弁護士 |
第2章 相続と登記の基本
空き家を売却したり、適切に管理したりするためには、まず「相続登記」の基本を押さえましょう。
相続登記とは何か(2024年4月から義務化)
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その名義を相続人に変更する手続きのことです。
- 義務化: 2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。
- 期限: 不動産の取得を知った日から3年以内に登記申請をしなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。
- 目的: 義務化の背景には、所有者不明土地の増加を防ぐという目的があり、空き家の問題にも直結しています。
相続放棄との違いと注意点
相続には「相続登記」の他に「相続放棄」という選択肢もあります。
- 相続放棄: 相続人が、亡くなった方のすべての財産と借金を含む権利義務を一切引き継がないようにする手続きです。
- 注意点: 相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
- 相続登記: 財産を引き継ぐことを前提に、名義を書き換える手続きです。
相続放棄をしていない限り、不動産を相続するなら相続登記が必要です。
遺産分割協議の必要性
相続人が複数いる場合、誰がどの不動産を相続するのかを明確にする必要があります。これが遺産分割協議です。
- 協議がまとまったら、その内容を記した遺産分割協議書を作成します。
- この協議書は、相続登記の必須書類となります。
- 相続人が1人しかいない場合や、遺言書で全て明確に指定されている場合は、遺産分割協議は不要です。
| 【豆知識】 司法書士に依頼できる範囲 <業務範囲> ・書類収集代行:戸籍謄本・住民票・評価証明書などの公的書類の収集 ・書類作成・申請代理:登記申請書、相続関係説明図の作成と法務局への申請代理 ・遺産分割協議書作成:遺産分割協議書の「雛形」提供や作成サポート <注意点> ・遺産分割協議書の内容決定や代理交渉は、紛争性がある場合は弁護士の領域となります。司法書士は、あくまで登記手続きに必要な書面作成をサポートします。相続者間のトラブル処理については、司法書士では対応できません。 |
第3章 登記変更に必要なもの
相続登記を行うために必要な、主な書類や条件を整理します。
相続人全員の同意と実印・印鑑証明書
最も重要なのは、誰が不動産を相続するのかについての相続人全員の合意です。
- 遺産分割協議が成立した場合、遺産分割協議書には相続人全員の実印の押印が必要です。
- 押印された印鑑が実印であることを証明するため、相続人全員の印鑑証明書が必要になります。
戸籍謄本・住民票などの収集
法務局は、提出された書類に基づいて、誰が相続人かを判断し、誰の名義に変更するのが正しいかを判断します。
- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本、住民票
- 固定資産評価証明書(不動産の所在地、面積、評価額を確認するため)
これらの収集は非常に手間がかかるため、司法書士に依頼することで大幅に負担を減らせます。
遺産分割協議書(相続人1人なら不要)
前述の通り、相続人が複数いる場合は、誰が何を相続するかを記した正式な文書が必要です。
固定資産税の納税者=登記名義人ではないことの説明
「はじめに」で述べたように、固定資産税の納税通知書が届いている人が、必ずしも法的な登記名義人であるとは限りません。
- 相続登記が未了の場合、税務署は相続人の中から代表者を選んで通知書を送っているだけです。
- 登記名義人は、法務局の登記簿に記載されている人物(多くは亡くなった方)です。
- 登記を変更するには、司法書士による登記手続きが必要です。
第4章 司法書士に依頼する流れ
相続登記を司法書士に依頼する場合の、一般的な手続きの流れを把握しておきましょう。
手続きのステップ
- 相談・打ち合わせ
- 相続関係や不動産の情報を伝え、手続きの内容、費用、必要書類などについて確認します。
- 必要書類準備・収集
- 司法書士が戸籍謄本などの収集を代行し、遺産分割協議書案を作成します。
- 署名・押印
- 作成された書類(遺産分割協議書、登記申請書など)に相続人全員が署名・実印押印します。
- 登記申請
- 司法書士が法務局へ書類を提出し、申請を代理します。
- 登記完了
- 法務局での審査が完了し、登記識別情報通知(権利証に代わるもの)などの書類を受け取ります。
必要書類一覧(主に司法書士が収集・作成するもの)
- 戸籍謄本(被相続人の出生から死亡まで、相続人全員の現在のもの)
- 印鑑証明書(遺産分割協議に参加する相続人全員)
- 住民票(新しく名義人になる相続人)
- 固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書または遺言書
- 登記申請書(司法書士が作成)
費用の目安(登録免許税+司法書士報酬)
相続登記にかかる費用は、主に以下の2つで構成されます。
- 登録免許税:
- 国に納める税金です。
- **固定資産評価額の0.4%**が原則です。
- 司法書士報酬:
- 司法書士に支払う手数料です。
- 不動産の数や難易度、書類収集の範囲によって異なりますが、一般的に5万円~15万円程度が目安となることが多いです。
自分でやる場合との比較
| 項目 | 自分でやる場合 | 司法書士に依頼する場合 |
|---|---|---|
| 手間・時間 | 大(特に戸籍収集と申請書作成) | 小(全て任せられる) |
| 正確性 | 誤りによる補正や再申請のリスクあり | 高(専門家による確実な手続き) |
| コスト | 登録免許税のみ(書類収集実費は発生) | 登録免許税+司法書士報酬 |
| メリット | 費用を抑えられる | 安心・確実、時間と労力の節約 |
相続登記は専門知識が必要であり、2024年4月以降は義務化されているため、専門家である司法書士に依頼するのが最も確実で迅速な方法と言えます。
第5章 司法書士を探す方法
実際に手続きを進めるために、信頼できる司法書士を探す方法を紹介します。
日本司法書士会連合会の検索システムの活用
全国どこでも利用できる最も一般的な検索方法です。
- 日本司法書士会連合会のウェブサイトにある**「司法書士検索」**システムを活用しましょう。
- 地域や相談内容(不動産登記、相続など)で絞り込むことができます。
岡山県司法書士会の活用
地域に特化した情報を得るには、地域の司法書士会が役立ちます。
- お住まいの地域、または登記をしたい不動産の所在地を管轄する
岡山県司法書士会のウェブサイトで、会員名簿や相談会情報を確認できます。
外部ページ→「岡山県司法書士会」
井原市周辺での検索例
岡山県司法書士会より検索した井原市に事務所を置く方の結果を以下に示します。(2025年9月時点)
- 阿部惠子(アベケイコ)
http://www.okayama-shiho.com/src/detail.php?id=93&t=1&f=1
事務所所在地: 井原市西江原町1291番地 阿部惠子 事務所0866-62-5544 - 小野雄史(オノユウジ)
http://www.okayama-shiho.com/src/detail.php?id=615&t=1&f=1
事務所所在地: 井原市井原町318番地1 小野雄史 事務所0866-75-4724
まとめ
空き家、相続、登記の問題は、放置すればするほど複雑化し、将来の売却や活用を妨げます。
- 行政書士と司法書士の役割の違いを理解し、不動産の登記変更は司法書士へ依頼しましょう。
- 2024年4月より相続登記が義務化されました。手続きは速やかに進めるのが適切です。
- 手続きには、名義人・相続人全員の協力と、戸籍などの書類準備が不可欠です。
- 登記に関する早めの相談によって、相続トラブルの回避、売却などの選択肢を広げられる可能性があります。
固定資産税の通知書にある「〇〇様 外〇名」という記載を解消し、ご自身の財産を適切に管理するためにも、まずは信頼できる司法書士に相談することから始めましょう。
<参照情報>
| 不動産登記法 | 不動産登記に関する基本法令。相続登記の義務化(2024年4月1日施行)や、登記申請の手続きの根拠。 |
| 司法書士法 | 司法書士の業務範囲に関する法令。登記申請の代理が司法書士の独占業務であることを定める根拠。 |
| 行政書士法 | 行政書士の業務範囲に関する法令。官公署に提出する書類等の作成を業務とすることを定める根拠。 |
| 地方税法 | 固定資産税に関する法令。共有資産の固定資産税は共有者全員の連帯納税義務であることを定める根拠(第10条の2など)。 |
| 法務省 | 相続登記の義務化に関する広報資料、Q&A、特設ページなど。 |
| 日本司法書士会連合会 | 司法書士の報酬に関するアンケート結果、専門家検索システムの提供。記事内の報酬目安(5万〜15万円程度)、登録免許税(評価額の0.4%)などの根拠となる一般的な相場情報。 |
| 各市町村の固定資産税関連ウェブサイト | 固定資産税の納税通知書が共有代表者宛に送付される仕組みや、代表者の選定基準に関する実務的な情報の根拠。 |
| 士業関連書籍・専門家ウェブサイト | 行政書士、司法書士、弁護士など他士業との業務範囲の違いに関する一般的な解説情報。 |